自分の行動をコントロールする方法として、「シュワルツ氏のルール」というやり方がありました。
シンプルで、誰でも実践できそうな方法なので、参考にしてみたいと思います。
- 33分33秒のタイマーをセットする
- その間コーヒーを飲んでもよい
- 壁を見ようと窓をじっと見ようとよそ見してもよい
- 33分33秒座っていれば、なにもしなくてもよい
- 広告(コピーライト)を書いてもよい
- どんな理由があろうと席を離れてはいけない
- その他の事をしてはいけない
- この33分33秒のセットを休憩を挟み、1日に6回繰り返す
1950~1970年にかけて活躍した、コピーライター界の超高給取り、Eugene Schwartz 氏のルールです。
Eugene Schwartz 氏のルール
- 33分33秒のタイマーをセットする
- その間コーヒーを飲んでもよい
- 壁を見ようと窓をじっと見ようとよそ見してもよい
- 33分33秒座っていれば、なにもしなくてもよい
- 広告(コピーライト)を書いてもよい
- どんな理由があろうと席を離れてはいけない
- その他の事をしてはいけない
- この33分33秒のセットを休憩を挟み、1日に6回繰り返す
つまり1日3時間労働。そこに一定のルールを作ったという事です。
仕事や勉強など、やるべきこと以外のことはやらない時間を設けるのがポイントみたいですね。
仕事や勉強は、やってもやらなくてもOK。
他にやることがないので、退屈しのぎで勉強や仕事をやってみる。
これなら、飽きっぽい性格の人でも、やるべきことをやれるように仕向けることができます。
→これ、すごいナイス・アイデアだと思いましたw
実は「何もしない」でジッとしているのは、結構苦痛だと思います。
だから、ついつい何かを始めてしまう。
そのとき、やるべきこと以外のことができない環境が用意されていれば、何かを始める=それが勉強や仕事になっている、という仕組みですね。
ただ、これが実際に使われていたのは1950年代ですから、当然現代とは明らかに「阻害要因」は違いますよね。
なぜなら、集中しなければならない物を阻害する事がこのルールの最大の目的ですから、現代、集中を最も阻害する物はネットだからです。
例えば作業現場などの実際の作業時に、ネットが仕事を阻害する事はまずありえません。仕事しますし。ところが、頭を使う仕事、デザインを作成する仕事、PCを使って何かを作成する仕事、いわゆるデスクでの仕事の場合は別です。
そのほとんどの仕事環境はネットにつながります。
なので、このネットを制する事が作業効率を最高の状態に保つための、最大のコツという事になります。
パソコンを使った作業だと、検索などのついでについついネットサーフィンをしてしまいがち。(時間のロスが発生)
パソコンでサイト閲覧を制限する方法はいろいろあるので、シュワルツ氏のルールと併用したら効果がありそうです。
ネタ帳で提案されていた現代版はこんなかんじでした。
現在利用しているルール
ネットは検索だけにとどめて、SNS、メール、その他ネットサーフィンはやらない、という制限を設けたらOK。
確かに、集中の阻害要因って、こういうのが多そうですね。
ただし、このようなルールを作っても、慣れないうちは、ちゃんと実践できないかも。
仕事中に一度でもFacebookを開くと、著しく生産性が低下するという話なんだけど、実際これは当たってるなぁと。
ただし、これはFacebookに限ったことではなくて、個人的に思うことは
1)自分でルールが作れない
2)自分で作ったルールが守れない
というこの2点に集約されるんじゃないだろうか。
人間、いつも意志力が強いってわけじゃないから、ルールが守れないときもあります。
- まずは1セットから始めてみる。
- 1セットの時間を短めにする。
慣れてきたら、33分33秒を6セット回せるようになると思います。
(最初から完璧にできる人がいたら、相当意志力が強いのかも?→ルールで自分を制御しなくても、別に困らないんじゃないかな?)
参考
他にも「シュワルツ氏のルール」で検索したら、参考情報がたくさんありました。
(結構有名な方法みたいですね?)
ポイントは
「しなければいけないこと」
を決めていることではなく
「してもいいこと、してはいけないこと」
と決めていることです。
彼は、自分のコピーライティングのスキルを向上することと献身的な調査を通して仕事の準備をすることに絶え間なく取り組んだ。
シュワルツは、自分の乗る船について学ぶことと調査をすることはハードワークであると言った。
彼は、調査ノートと大まかな概略と共に開いたページの前にただ座っていた。
彼は、通常、飽きるまで数分間椅子に座ったままでいて、それからゆっくりとタイプを始めた。
タイマーが切れると、たとえ文章の途中でも中断し、10分か15分間好きなことをしに席を立つ。そしてまた戻って来て同じことをするのだ。
自分の乗っている船の概略と調査が燃料だったが、キーは退屈だった。30分か何もせずに座っていることが退屈へと導く・・・だから彼は書いた。
- まずは何もしないで、自分を「退屈」な状態に追い込む。
- 退屈になって痺れを切らすと、退屈しのぎで何かをやりたいという状態になる。
- 何かを始めたくなったときに、目の前にある仕事をやれば良い。
「退屈さ」が行動を促すポイントになっていることが、目からウロコでした!
今までは「退屈」や「怠惰」はいけないもの、排除すべきものだと考えていたけど、これをうまく利用すれば、逆に成果を上げられるんですね?
(怠け者にはピッタリの方法かも!?www)
→シュワルツ氏は、仕事に取りかかる前の事前準備はしっかりやっていたそうなので、ただ退屈ってだけでは、仕事に没頭することはできませんね?
(そこを勘違いすると、本当に33分間何もしないで終わってしまうだけかもw)
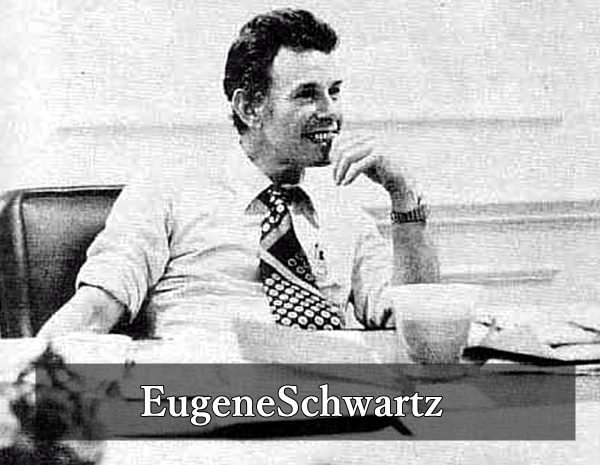
この法則の特徴的なところは、
「やらなければいけないこと」を決めるのではなく、
・やってもよいこと
・やってはいけないこと
を決めている点。
そうすることで、自分の意志で決めた形になるので、遂行しやすくなるわけです。
なぜ、時間を測ってやるのか?
時間が無限にあるのと、「時間があと30分しかない」と思ってやるのでは、作業効率が全く変わるからです。33分33秒は必ず作業に集中すると決めておくとパーキンソンの法則が働きますので、ずーっと区切り無く作業をするのとでは全然効果が違います。
仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する

夏休みの宿題は最後の日にやるみたいに、与えられた時間を全部使って、締め切り直前になって本気を出す。
最初から本気を出すためには、締め切りを早くしておく=持ち時間を短く設定しておけばOKと。
ポモドーロ・テクニック
シュワルツ氏のルールと似た方法として、「ポモドーロ・テクニック」という時間管理法もあります。
集中して仕事をこなすために、25分毎に時間を区切って仕事をする時間管理術。Francesco Cirillo氏が1992年、自身の勉強効率を上げるために考案した。
手順
- 25分を1ポモドーロとし、やるべきタスクを1ポモドーロ刻み(25分毎)に分ける。
- 25分間は、他の事は一切やらず、タスクに集中する
- 25分経てば、5分間の休憩を入れる
- 4ポモドーロ毎(2時間毎)に30分程の長い休憩をとる
- 後は上記を繰り返す
時間の区分は、25分でも33分でも、自分の状態に合わせて、短い時間から徐々に伸ばしていけば良いと思います。(人間の集中力は15分程度という話もあるので)
まとめ
- 33分33秒を1セットにして、タイマーで計る。
- 何もしなくてもOK
- 仕事や勉強をやってもOK
- 他のことはやらない
- 1セットが終わったら、必ず休憩を入れて、10分~15分休む。
- これを1日6セット繰り返す。
ポイントは、
- 「やるべきこと」を決めるのではなく、「やってもよいこと」と「やってはいけないこと」を決めておく。
- 何もしないと退屈になり、退屈しのぎで何かやりたいと思うようになる。
- 何かをやりたいときに、「やってもよいこと」を着手すればOK
「退屈さ」の心理をうまく利用して、仕事の生産性を改善してみたいと思います。

- 作者: Staffan Noeteberg,渋川よしき,渋川あき
- 出版社/メーカー: アスキー・メディアワークス
- 発売日: 2010/12/16
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 13人 クリック: 330回
- この商品を含むブログ (56件) を見る
